

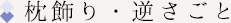
病院から自宅に遺体をお運びしたら、布団に寝かせます。敷ぶとんは一枚、その上にシーツをかけ、掛けぶとんは一枚にします。安置する場所は仏間あるいは座敷で、故人の頭を北に向けて安置します。
この時、故人の身体にドライアイスを目立たないように使用します。顔には白布をかけ、両手を胸の当たりで合掌させ、手には数珠をもたせます。事情によって北枕に出来ないときには、西枕にします。
遺体を安置したあとには「枕飾り」を準備します。故人の枕元に、白布をかけた小机を置きます。
その上に
(1)ローソク立て
(2)香炉
(3)花立ての三具足の他
(4)鈴(りん)
を用意して下さい。花立てにはシキミや白菊を飾ります。これを俗に「一本花」ともいいます。
そして線香立てやローソク立てには、それぞれ線香、ローソクを立てて火をつけます。
線香とローソクは消えないように、遺族の人が交替で見守っていてください。
※浄土真宗では水の中にシキミ一枚、あるいは花びら一枚を浮かべることがあります。
「枕飯」は故人の使った茶碗を用意しご飯を山盛りにし、その上に箸を一本を立ててお供えします。
「枕団子」を作り白紙を敷いた三方に供えます。
また故人の枕元か胸の上に、葬儀社で用意した「守り刀」を置きます。
遺体を北向きに寝かせ、案(台)とよぶ白木の八足の上に三方を置き、そこに洗米、塩、水、お神酒を器に入れて供えます。
三方の左右には真榊、ローソクを置きます。
キリスト教では本来、枕飾りの習慣はありませんでしたが、台の上に十字架、聖書、生花を飾り、ローソクの火を絶やさないようにすることが多いようです。
仏典『涅槃経』に、
「その時世尊は右脇を下にして、頭を北方にして枕し、足は南方を指す。面は西方に向かい」
とあるように、釈尊が入滅されたとき、頭を北にし顔を西に向けられた姿を故事に由来します。
この頭北面西は古くから伝わっており、法然上人の伝記のなかにも、「建暦二年、正月二十五日遷化。…頭北面西にしてねぶるがごとくにしておわり給いにけり」とあります。
枕飾りのローソクの光は仏の光明を意味し、線香の煙は仏の食物を意味しています。又灯りは死者が迷わないように道を照らすという意味があります。「一本花」に用いるシキミは、神の意志の先触れをするとされる木で、その実が毒のため、「あしき実」からシキミと呼ばれるようになったといわれています。大変に生命力の強い木で、魔除けにもなるので昔から墓などにも植えられました。
「枕飯」は、食物が肉体を養うならば、魂も養うという考えから、魂の形である丸形にして供えます。これは死者の依代(よりしろ)と考えられています。
「枕団子」は、釈迦が入滅したときに無辺身菩薩が香飯を捧げた故事に基づいています。また地域によっては、死んでから善光寺に行くための弁当という信仰があります。
枕団子の数は六個が多く、これは六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六世界)を巡る象徴で、六文銭を死者が身につけていくのも同じ考えの現われです。
「守り刀」は邪霊を払うために用いると言われています。また武士が死んだとき、枕元に刀を置いた名残りともいわれています。
上新粉(米の粉)をぬるま湯でかためによく練ります。
(1) 直径3センチくらいの団子を11個作ります。
(2)小皿を用意します。
(3)皿の真ん中に一個置き、その回りに6個置きます。
(4)7個の上に3個置きます。
(5)1番上に1個置きます。
(6)5分程度蒸して完成です。
※浄土真宗ではお供えしません。
葬儀に関係するものごとでは、通常の逆に行なう「逆さごと」というものが行なわれています。
例えば死者の衣装(帷子)を左前に着せる。枕元に屏風をひっくり返して立てる「逆さ屏風」。
水にお湯を注いでぬるくする「逆さ水」。死者のふとんを天地逆さにする「逆さ布団」といった作法が残されています。
死という異常事態に対処するために、古来よりさまざまな工夫がなされてきました。
それは死を生者の領域から隔絶させるための演出というべきもので、それが「逆さ事」という形であらわされました。
また死者の世界はこの世とは「あべこべ」になっていると考えられ、例えばこちらの昼が向こうでは夜ということは多くの民族で信じられていました。
そこで、かつて葬儀が夜行なわれたのも、死者が向こうに渡るのに、明るいのがよいというので、こちらでの夜に葬儀を執り行なったといいます。
昔から神道では死や出産などを汚れとして取り扱いました。
棺時に足袋を右左逆にはかせたり、洋服の裾を顔の方に、着物の襟を足元に掛けるという「逆さ着物」は、最近でもよく行われている風習です。
水にお湯を注いでぬるくします。湯灌(ゆかん)の際などに行います。
屏風の絵柄を天地逆にして枕元に立てかけます。
こま結びを縦に結んだもの。普通は横に結ぶことの逆をします。
相手から見て左の衽(おくみ)を上にして着物を着せます(普通は右前)。
亡くなった人の衣装をさかさまにしてかぶせます。襟を足のほうにして着せるので、逆さ着物といいます。
死にゆく者に対して、家族が枕元に寄って順番にその口許を水でうるおすことを「末期の水」あるいは「死(に)水」をとるといいます。新しい筆か、箸の先に脱脂綿を巻いて糸でしばり、それに水をふくませて、軽く口を湿らせます。この作法は、本来死者の命が蘇ることを願って行うもので、死者に何かをしてあげたいという遺族の心情にふさわしい儀式といえるでしょう。
かつては臨終の間際に行なわれるものでしたが、現在では息を引き取ったあとに行います。
死水をとる順序は一般に喪主、そして血縁の近い順とされています。
最初は配偶者、次に子、そして故人の両親、兄弟姉妹、子の配偶者、孫の順となります。
・死水をとるのは、ご遺体が病院から自宅に帰ってきて、布団に安置された直後に行われます。
・家族がそろっているとよいのですが、揃っていない場合には、揃うのを待って行うことがあります。
・道具は箸の先に脱脂綿を巻き付け紐で縛り、それに水をふくませて唇を湿らすのです。
・脱脂綿の代わりに、しきみや菊の葉に水をつけ、それで死水をとることもあります。
仏典『長阿含経』の中に「末期の水」の由来となる話がのっています。
「末期を悟られた仏陀は弟子の阿難に命じて、口が乾いたので水を持ってきて欲しいと頼んだ。
しかし阿難は河の上流で多くの車が通過して、水が濁って汚れているので我慢して下さいと言った。
しかし仏陀は口の乾きが我慢できず、三度阿難にお願いをした。そして『拘孫河はここから遠くない、清く冷たいので飲みたい。またそこの水を浴びたい』とも言った。その時、雪山に住む鬼神で仏道に篤い者が、鉢に浄水を酌み、これを仏陀に捧げられた」とあります。これが仏典にある「末期の水」の由来です。